日本列島には、古代から現代にかけて多様な城や防衛施設が築かれてきました。
縄文時代の初期、人々は自然の脅威や外敵から身を守るためのシンプルな横穴住居を掘ったのが始まりでした。
しかし、社会が進化し、異なる部族や国家間の競争が激化する中、より高度な防衛技術や施設の必要性が生まれてきました。
弥生時代に入ると、集落の中心に堀や土塁を持つ環濠集落が現れ、その後の古墳時代では、豪族たちの力を示す巨大な古墳とともに、豪族の居館が建設されました。
これは、後の時代の武家屋敷や城の原型となったものです。
また、6世紀から7世紀にかけての神籠石や天智天皇の時代の山城は、外国の技術や影響を受けつつも、日本独自の特色を持つものとなっています。
さらに、都城制の導入により、都市の中心には壮麗な宮殿や城が築かれるようになり、都市計画そのものが防衛を意識したものとなりました。
今回の記事では、このような日本の城や防衛施設の歴史的背景と進化の過程を詳細に探ることで、日本の歴史や文化、技術の発展を理解する鍵について解説します。

各時代の社会的背景や技術の進展、そして外部からの影響との関連性を踏まえながら、日本の城と防衛の壮大な歴史を読み解いていくんだワン!
日本古代の城と防衛!縄文時代から古墳時代までの進化とは?
城や防御施設の考え方は、人類の歴史を通じて見受けられます。
縄文時代には、猛獣や他の部族から身を守るために横穴住居を利用していました。
こうした自己防衛の必要性が次第に城の構築へとつながりました。
一時期、城の起源は神籠石や東北の城柵にあったとされていましたが、弥生時代の集落の調査が進むにつれ、その考え方が変わりました。
弥生時代の高地性集落が城の原初形態であると考えられるようになったのです。
これは、山や丘の上に作られた集落で、特にその地形を利用して防御性を高めていました。
この考え方が進化し、平地に移った形が環濠集落となりました。
これは、堀で囲まれ、柵で守られた集落で、その形状は完全に城そのものです。
特に、神奈川県の大塚遺跡や佐賀県の吉野ヶ里遺跡は、この時代の環濠集落の代表例として知られています。

次に古墳時代になると、防御的な集落は少なくなり、代わりに地域を代表する豪族が巨大な古墳を建造し始めました
これらの豪族は、自らの居館も構築し、その中でも群馬県の三ツ寺遺跡は特に注目されています。
この遺跡は古墳時代中期の豪族の居館と考えられ、その構造は非常に大規模でした。
このような古墳時代の豪族居館は、後の時代の武士の居館の原型となったと考えられています。
要するに、人々は古代から身を守るための施設を持っていて、その形や方法は時代とともに変わりつつも、その必要性は変わらず続いてきました。
古墳時代から天智天皇の時代!日本の初期山城と城柵の展開とは?
古墳時代の四世紀から六世紀には、九州や中国地方に「神籠石」と呼ばれる山城が築かれました。
この神籠石が実際に城なのかについては、明治時代以降、長い間論争が続いていました。
しかし、戦後の発掘調査で朝鮮式の山城との類似性が明らかになり、今では古代の山城と認識されています。
具体的な例として、佐賀県の帯隈山神籠石や久留米市の高良山などが挙げられます。
しかし、いつ、誰がこれらの神籠石を築いたのかは不明で、一つの説としては地方の豪族が大和朝廷に対抗するために築いたとされています。
天智天皇の時代には、唐や新羅からの侵攻に備えて、朝鮮から来た技術者の協力を得て、朝鮮式の山城が築かれました。
福岡県の大野城や基肄城は、その代表例であり、石や土で強固に造られています。
また、この時期には水を利用した「水城」も築かれ、『日本書紀』にも記録されています。
天智天皇は626年に飛鳥で生まれ、その当時の名前は中大兄皇子でした。
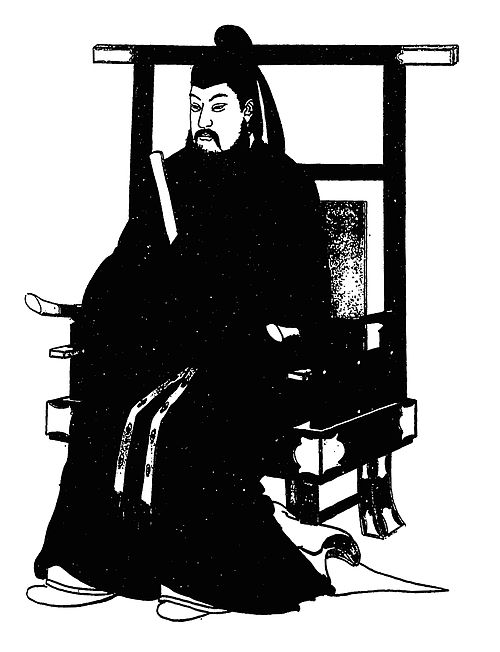
彼は蘇我入鹿という権力者と対立しており、中臣鎌足と共に彼を暗殺した事件でよく知られています。
663年の白村江の戦いでは唐と新羅の連合軍に敗北し、その後の唐からの攻撃を警戒して、667年に都を近江大津宮に移しました。
その翌年に天智天皇として即位しました。
彼の時代には日本初の全国的な戸籍である庚午年籍の作成や、時間を示す漏刻の設置など、多くの制度や文化の発展が見られました。
しかし、彼が即位してからわずか4年後の671年に亡くなり、その後の壬申の乱によって大津宮は使用されなくなりました。
また、大和朝廷は東北地方の蝦夷を征服し、その地域に「城柵」と呼ばれる軍事拠点や開拓のための拠点を築きました。
これらの城柵は、7世紀から8世紀にかけて北上し、著名な将軍である坂上田村麻呂が東北の蝦夷を征服し、その地域を統治するための拠点として使用しました。

これらの城柵は非常に大きく、例として多賀城や秋田城があるよ。

東北地方には「方八町」と呼ばれる地域があり、城柵が存在したと考えられているんだワン!
日本の都城制と中世の城郭の進化とは?
日本の都城制の起源は、孝徳天皇が大化元年(645年)に難波の長柄豊碕に都城を設置したとされています。
しかしこれについては最近の調査で明確ではなく、藤原京が実際の都城制の初めと考えられています。
天武天皇が壬申の乱で勝利した後、中央集権を強化するために新しい都を建設しようとしたが、彼の死により中断されました。

矢田山金剛寺 蔵 出典:wiki
後に持統天皇がこれを再開し、694年に藤原京が完成しました。
藤原京は大和三山に囲まれた地域に設置され、条坊制という碁盤目状の都市計画を採用していました。
その後、元明天皇の時代に平城京が建設され、この都市は当時の長安に影響を受けていましたが、規模はやや小さかった。
そして、平安京が建設され、その計画は平城京と似ていましたが、道幅などにいくつかの違いがありました。
平安京にも羅城門がありましたが、これは日本独自の形として、中国の都城制を模倣して作られたもので、実際の防御の役割はほとんど果たしていなかったと思われます。

出典:都市史05 羅城門 – 京都市
※参考:都市史05 羅城門 – 京都市
また、堀という防御の方法には「空堀」と「水堀」があり、中世の城にはさまざまな形状の堀が掘られていました。
初期の堀はV字型で、後には鉄砲の普及に伴い、堀の幅が広がり、底が平らな箱堀が主流となりました。
堀の幅には特定の規格はありませんでしたが、現存する遺構を見ると、20メートルから60メートルのものが多く、近世の城には100メートル以上のものもあったと言われています。
総括
日本の城や防衛施設の進化は、その土地の歴史や文化、そして技術の成熟を映し出す鏡のような存在であることが明らかとなりました。
縄文時代の初期の防衛の必要性から始まり、社会の成長とともに、その形や機能は変わり続けました。
しかし、その核心にあるのは、常に人々の安全や生活を守るという原則でした。
弥生時代の環濠集落や古墳時代の豪族の居館、そして古代の神籠石や中世の山城、さらには都城制に代表される都市の中心の城。
それぞれの時代において、その時々の技術や文化、外的な影響を取り入れつつ、日本独自の進化を遂げてきました。
これらの城や施設は、単なる建築物や土木構造ではなく、時代時代の人々の生活や思考、そして歴史に対する姿勢を表しています。
それは、外敵からの防衛だけでなく、自らのアイデンティティや文化を守り、発展させるための手段でもありました。

この歴史的な探求を通じて、私たちは日本の城や防衛施設が持つ多面的な価値や意義を再認識することができたね。

それは、現代においても私たちの生活や文化、アイデンティティを理解し、未来に向けて発展させる手がかりとなるんだワン!
※この記事の理解を深めるために、「日本の古代から中世の防御施設の変遷クイズ」で理解度チェックをしましょう!
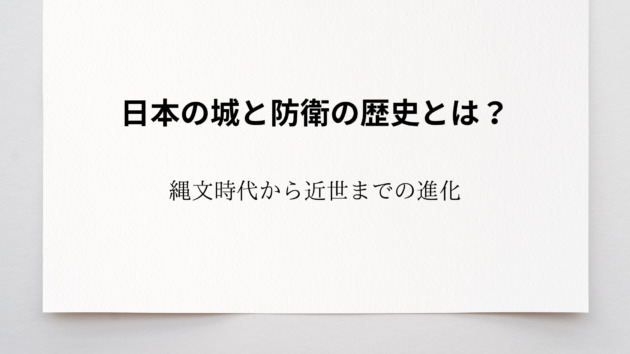


コメント